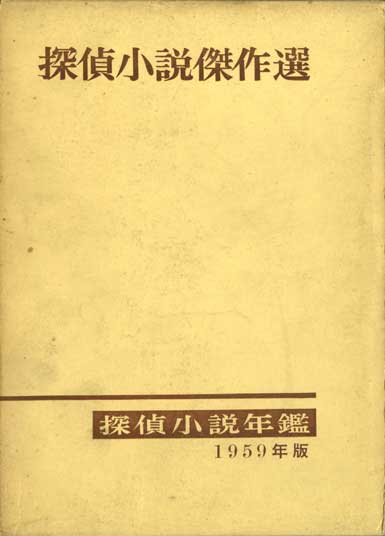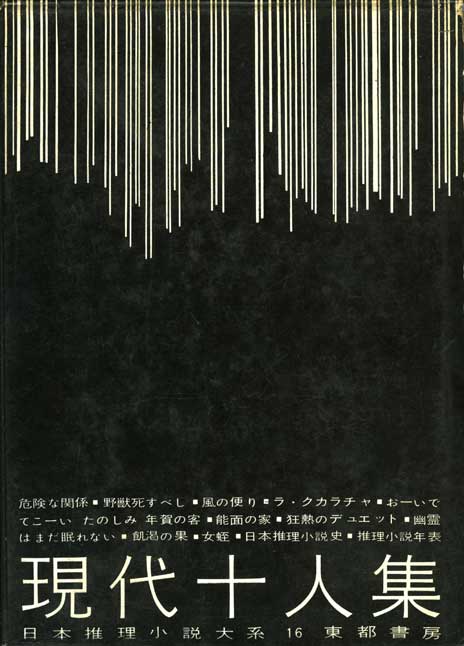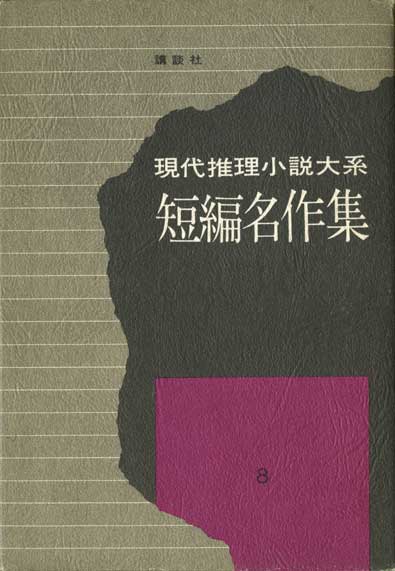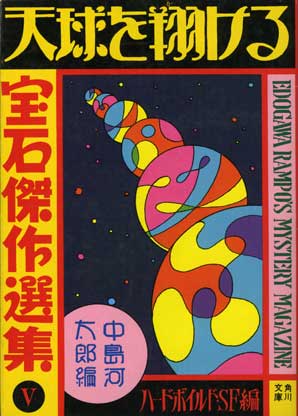「X橋付近」の時代
「X橋付近」まで
ーーーまずは生い立ちから。
高城 昭和10(1935)年に北海道函館市で生まれました。だけどすぐに親父の仕事の関係で宮城県の仙台市に引っ越した。親父は函館商業学校の英
語教師をしていたのですが、昭和14(1939)年に、仙台高等工業学校に移りました。これは戦後には東北大学の工学部になった学校ですね。だから、僕も四歳までしか函館に
は住んでいない。幼稚園の時に仙台に引っ越したわけです。ところが仙台で小学校に入学したと思ったら、今度は秋田県の比内町に疎開です。疎開といっても比内町は親父の
故郷なんです。仙台も米軍機の空襲を受けるかもしれないと、親父が僕ら兄妹を故郷に避難させたんです。親父の実家に預けられたようなものです。終戦は小学校5年生、ちょ
うど10歳の時でした。戦争が終わって、やっと仙台に家族そろって落ち着くことができました。仙台では、東北学院中学・東北学院高校を経て、東北大学文学部に進んだ。専
攻は英文学です。大学卒業後は北海道新聞社に入社して、以来ずっと北海道に暮らしています。
ーーー「X橋付近」で小説家としてデビューするのは昭和30年ですから、まだ東北大学に在学中のころのことですね。学生時代から小説家志望だっ
たのですか。
高城 いや、それがまったくそんな気はなかったんですよ。そもそも小説でメシが食えるなんて考えられない時代でした。もちろん大作家はいまし
たよ。だけど、あまりにも遠い存在で、自分がなれるなんて思えない。推理小説でデビューしましたが、推理小説そのものが今と違ってまだまだ世の中に認められてはいなか
った。あのころ推理小説で食べていけたのなんて、江戸川乱歩さん、木々高太郎さん、大下宇陀児さんくらいだったんじゃないかな。
ーーーどうして小説を書き始めたのですか。
高城 とにかく文章を書くのが好きな子どもだったんですよ。小説を書き始めたのは東北学院高校のころです。冒険小説みたいなものを書いては少
年雑誌に投稿していました。当時は『潭海』とか、少年向けの小説雑誌がたくさんあったんです。ところが、まったく相手にされなかった。子どものくせに、大人向けみたい
な小説を書いていたんですよ。犯罪組織や秘密結社が暗躍する荒唐無稽なギャングものです。少年雑誌に送るのに、なんと登場人物に子どもが一人もいない。また、長いんだ
これが。飽きもせずによくまあ高校生が大長編を書いたものだと思いますよ。とにかく、とてもじゃないが採用されるような代物ではなかった。「これは大人向けの小説です
。うちには掲載できません」なんてみんな送り返されてきました。早熟といえば早熟だったんでしょうね。
もっとさかのぼるとね、小学生のころ、疎開先の親父の実家に、子ども向けの探検家の伝記がたくさんあったんです。リビングストンやヘディン
、スタンレーなど欧米の探検家の伝記ですね。なぜあんなのがそろっていたのか、今考えると不思議ですが、とにかくそれをむさぼり読んだ。すっかり感化されちゃって、よ
し、僕は大人になったら探検家になるんだって小学生が決意してしまった。「ヘディンもラサには行けなかった、俺はいつか行ってやるぞ」なんて意気込んでいた(笑)。
だけど「探検家になるんだ」って言っても大人たちはだれも本気にしてくれない。みんなに笑われておしまいです。だんだん恥ずかしくて口にも
出せなくなった。そこで、探検家になるにはどうしたらいいのか、心のなかで秘かに作戦を練ったんです。今度は「探検家になるには科学を知っておいたほうがいいだろう。
まずは科学者になってそれから探検家になろう」と路線を変更しました。『子供の科学』なんかを一生懸命に読んで、工作に熱中して、科学者になる準備を始めた。戦争中の
子どもたちの夢といえば、陸軍大将か海軍大将ですよ。そんな時に、僕は「いや、科学者になっていろいろと発明するんだ」なんて言ってました。
ところが中校生くらいになって、どうも自分は科学者にはなれそうもないと自覚し始めた。だいたいそのころは、日本人は自由に海外にも出られ
なかった。科学者になってから探検家になんていったって、海外に出かけることもできないんじゃしかたない。まずは海外に出ることができる仕事に就かなければならない。
なにかないかと知恵を絞ったら、新聞記者があったんです。海外特派員になって世界の秘境を目指そう、というわけですね。ここでまたまた路線変更です。新聞記者になるた
めにはまずは文章修業だ、とさっきも言ったように少年雑誌に盛んに投稿を始めた。大学で英文学を学んだのも、海外に行くためには英語が必要だと思ったからです。書き始
めてみたら、自分が文章を書くのが好きだということに気が付いた。高校から大学と投稿を続けているうちに、乱歩さんの『宝石』の懸賞小説、まあ、今でいう新人賞に一席
で入賞してデビューしたわけです。大学2年生の時のことです。掲載が昭和30年の1月ですね。締め切りはいつだったんだろう。だけど、執筆は昭和29(1954)年だったことに
なりますね。
デビュー後も『宝石』を中心に作品を発表させてもらいましたが、原稿料が安いうえ、支払が遅いんです。とてもじゃないがこれでは食べていけ
ないなと思いました。だけど『宝石』も、経営がよほど苦しかったんだろうね。
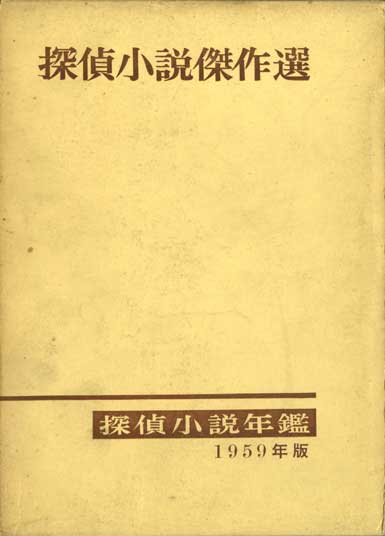
仙台でハードボイルドを
ーーー推理小説、それもハードボイルドというジャンルを選んだのはなぜだったのですか。
高城 高校あたりから推理小説好きになったのですが、きっかけはやっぱり『宝石』との出会いだった。高校時代に初めて読んで、これは面白いと
推理小説に目覚めてしまった。古本屋に行って『宝石』のバックナンバーを買いあさっては読んでいました。だけど、戦前の探偵小説のメッカ『新青年』まではさかのぼらな
かったね。本格モノよりもハードボイルドが好きだった。レイモンド・チャンドラーやダシール・ハメットが、戦後になって盛んに翻訳されていました。ハードボイルドとい
っても、いまみたいにポピュラーじゃなかった。終戦と同時にどっと入り込んできたアメリカ文化の1つです。これはいったいなんなんだという感じです。とっても新鮮だった
。卒業論文のテーマはヘミングウェイでした。ハードボイルドの元祖はアーネスト・ヘミングウェイだという。いったいどんな小説なんだろうと卒論にことよせて読んでみた
んです。
アメリカ文化にはあこがれましたよ。家庭環境もあって、ひと一倍に大きな影響を受けたかもしれません。親父が英語の教師だったでしょう。英
語を話せる日本人が少ない時代でしたから、進駐軍との付き合いが深かったんです。正式な通訳というわけじゃなかったけれど、なにかと頼みにされたようです。親父が付き
合っていたのは将校クラスの軍人たちでしたね。うちにも進駐軍の軍人が奥さんを連れて遊びに来たりしていました。
親父としてはアメリカの物資や情報が欲しかったんでしょう。苦竹にあった進駐軍の基地にも出入りしていたようです。僕も親父にくっついて基
地に行った覚えがあります。食料も配給制だった時代です。米兵が持ってきてくれる缶詰やお酒がものすごく珍しかった。親父がもらってきたバーボンのラベルにびっくりし
たのを覚えていますよ。「フォア・ローゼズ」でした。真っ赤なバラの花がきれいに印刷されていた。ホントにきれいだった。親父もそう思ったんでしょう。しばらくの間「
フォア・ローゼズ」の瓶を飾って眺めていましたよ。
だけど親父は食べ物やお酒よりも本を手に入れたかったんじゃないかな。アメリカの本なんて戦争中はまったく手に入らなかったわけですからね
。進駐軍の軍人によく本をもらっていました。ペーパーバックの娯楽小説もたくさんあったのですが、そのなかにチャンドラーやハメットのハードボイルドもあったんです。
中学生のころですから、自分ではまだ読めなかったんだけど、高校に入ってからぼちぼちと読み出した。本格的に読み始めたのはやっぱり大学に入ってからです。ハードボイ
ルドに魅力を感じたのは、それまでの日本にはなかった新しいタイプの小説スタイルだったからでしょうね。
そんな時に『宝石』の新人賞を知ったわけです。大学新聞は辞めてしまったけれど、文章修業はしたい。推理小説というのも面白そうだ。これは
ちょっとやってみてもいいんじゃないか。どうせ書くのなら、ハードボイルドという新しいスタイルで書いてやろうと思いました。こうして『宝石』に送ったのが「X橋付近
」だったんです。
あと、ハードボイルドということでいえばね、僕がデビューした昭和30年前後には、ハードボイルドを意識した小説家が立て続けにデビューして
いるんですよ。これがみんな同じくらいの年ごろなんだ。戦争が終わってアメリカ文化がどっと入り込んでくるなかで、みんなハードボイルドに出会って「これはなんだ」と
衝撃を受けた。アメリカ文化の影響下に学生時代を過ごして小説を書き始めた戦後最初の世代が僕らだったんじゃないかな。「占領」って文化的にも精神的にもやっぱりイン
パクトがあったんですよ。大藪春彦、河野典生、そして僕の3人が「ハードボイルド三羽烏」なんて呼ばれましてね。『宝石』の「ハードボイルドとはなんぞや」みたいな特集
に揃って登場したりしましたよ。
ハードボイルドといっても、日本にそんなジャンルはなかったんですよ。みんな手探りで書かなければならなかった。現在の読者からみれば「こ
んなのハードボイルドじゃない」と思うかもしれないけれど、試行錯誤の時代だったんです。日本にハードボイルドは定着しないんじゃないかなんて論争があったくらいです
。『新宿鮫』とか『不夜城』なんてとんでもない。肝心の歌舞伎町がまだなかったんだから(笑)。
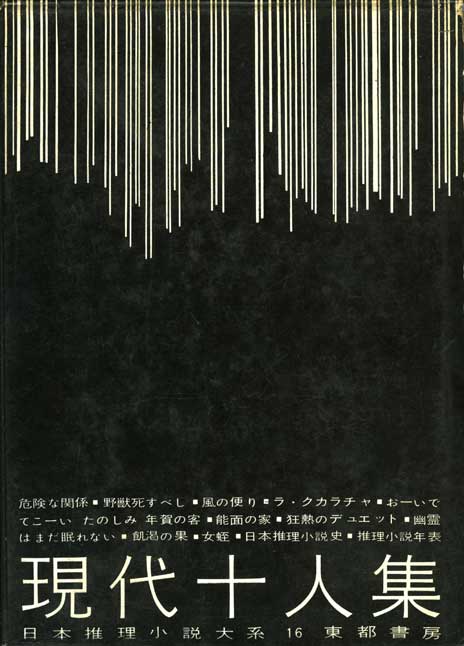
占領下の仙台
ーーー敗戦からデビューにかけてのころはどのような暮らしだったのですか。
高城 小学校五年生の時に戦争が終わって仙台に帰ってきたでしょう。だから僕は昭和20年7月9日の仙台空襲を知らないんです。自宅は現在の立町
小学校のすぐそばにありましたが、空襲で見事に燃えてしまいました。しばらくはなんとか焼け残った物置きに暮らしていたんですよ。その後、抽選で当たったのでしょうか
、簡易住宅というやつに住めることになりました。今でいうプレハブですね。板を組み合わせたパネルみたいなのを使った粗末な建物です。どうしても不便だというので、親
父はなんとか新築したかったようですが、終戦直後でしょう。材木がないんですよ。日本中が復興中ですからね。個人の住宅の再建になんて材木がなかなかまわってこない。
手に入ってもとにかく値が張る。ところがよくしたことに、比内町の父親の実家が別荘を持っていたんです。その別荘を解体してもらって、仙台に運ぶことになった。そのほ
うが新しい材木を手に入れるよりも安あがりだった。結局、別荘を仙台に移築したんですけれど、なんだか奇妙でしたよ。焼け野原に数寄屋ふうの家がぽかんと建っているん
です。この家で大学時代まで過ごしました。
当時の仙台は、空襲の痛手から立ち直っていませんでした。高校時代まではまだまだ焼け野原だらけでした。高い建物なんかまったくなかった。
道路だけがだだっ広くて町全体がやけに広々としていました。目に見えて復興し始めたのは昭和28年、大学に入ったあたりからです。中央通や一番町は、もうかなりにぎやか
でね。アーケードも既にできていたんじゃないかな。
中学高校と、映画マニアでした。暇さえあれば映画を観ていました。一番町にたくさん映画館が並んでいてね。中学校の同級生に酒屋の息子がい
たんです。成績も悪いし、暴れん坊だし、とにかく問題児だった。だけどなぜか僕とはものすごく仲がよかったんです。こいつが仙台市内の映画館ならどこにでも顔が効いた
。きっと家業となにか関係があったんでしょう。おかけで僕もどこの映画館も顔パスで入れるようになったんです。歴史に残る名作から、B級のギャング映画まで、あのころ
の映画という映画はほとんど観ていますよ。この友達は早くに亡くなってしまいました。
東北大学に入って、2年生までは仙台市郊外の富沢の校舎に通っていました。戦争中は軍の施設だった、なんだかぼろぼろの建物でした。大学時代
はスポーツはフェンシングをやっていました。大学にはフェンシング部がなかったので市の体育館でやっていました。フェンシングは北海道でも続けました。
あとは音楽ですね。ジャズも好きだったけれど、ラテン音楽も大好きでした。特にタンゴね。いまみたいにオーディオ機器が普及している世の中
じゃありませんでしたからね。レコードとプレーヤーを手に入れて、町中の会場を借りる。そして、入場料を取って聴かせるレコードコンサートが成立した時代です。タンゴ
に夢中になったあまり、スペイン語の勉強までしましたよ。
ただ、米軍が駐留していましたからね。いかにも占領中でした。仙台駅前には夜な夜な「パンパン」、つまり米兵相手の売春婦がずらりと立って
いた。苦竹の米軍基地周辺には「オンリー」と呼ばれた米兵のお妾さんの家がたくさんありましたよ。仙台駅のすぐそば、それこそX橋の付近は、小説に書いた様子そのまま
の特飲街です。酒も飲ませれば、売春もやっていた。まあ、私娼窟といってもいいかな。ピンクの照明が通り沿いにぱーっと並んでいてね。米兵が次々に出入りしていた。物
好きで見物に行ったことはあるけれど、僕ら学生はあんまり近づきませんでした。やっぱり物騒でしたよ。学生が酒を飲むといえば、安全な一番町の裏通りでしたね。
占領中は米軍関係者はそれは威勢がよかったですよ。乗用車なんて普通の日本人には縁がなかった時代でしょう。それどころかクルマ自体が珍し
かったのに、進駐軍の将校連中の奥さんなどは平気で町を乗りまわしていました。一度、交通事故を見たことがあります。将校の奥さんらしき白人女性が、自転車の男をどん
とひき倒したんです。ひかれた男は頭から血を流して倒れている。あわてて日本人の警察官がやってきた。すると白人女性が車から出ようともせず警察官に向かって英語でな
にごとか大声でまくしたてるんです。「わたしが悪いんじゃない、この自転車の男が悪いんだ」というわけですね。白人女性の剣幕に、警察官は逆にぺこぺこ頭を下げている
。言うだけ言うと、女性はなにごともなかったかのように走り去りました。こんな横暴が許されていた時代です。
ーーー「X橋付近」と「ラ・クカラチャ」は、そんな時代の仙台を舞台としていますね。
高城 仙台を舞台にハードボイルドを書いてみようとした時、自然と当時の世相に目が行ったんです。チャンドラーならロサンゼルス、ハメットな
らサンフランシスコ。やっぱりハードボイルドは都市の暗黒面を描くみたいなところがあるでしょう。自分で書く場合にも、どうしても仙台の物騒な面にひかれた。それが「
X橋付近」と「ラ・クカラチャ」だったといっていいでしょう。
ーーー「高城高」というペンネームはどこから思い付かれたのですか。
高城 どうして付けたのか、これがあんまりよく覚えていないんですよ。僕もこのペンネームは「X橋付近」で初めて使ったと思い込んでいたんだ
。ところが今回、ちょっと気になって調べてみたら、デビュー前の『文藝首都』でもこのペンネームを使っているんだなあ。なんとなく記憶にあるのはね、仙台といえば土井
晩翠の名曲「荒城の月」が有名だから、漢字を換えて「荒城」をいただこう。だから「高城」は「タカギ」ではなく「コウジョウ」です。名前の「高」も「コウ」なんですが
、こちらはどうしてこうなったものかねえ。ただ単に語呂がよかったからなんじゃないかな。
ーーーデビューした時の周囲の反応はどうだったのですか。
高城 さっきも言ったように推理小説っていっても、世間的にはマイナーだったからね。ほかに推理小説好きの友達もいなかったし、仲間たちもだ
れも知らなかったんじゃないかな。僕自身もこのまま小説を書き続けようという気もなかった。当時は現実的にモノを書いて食べていくといったら、新聞記者くらいしかなか
った。僕もあくまで新聞記者になろうと思っていました。
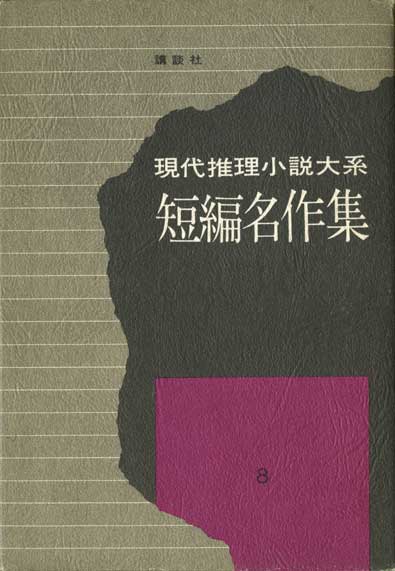
北海道時代
ーーー大学を卒業して北海道新聞社に入社されるわけですが、なぜ道新だったのですか。
高城 昭和30年代には、地方紙ではなんといっても道新がユニークだったんですよ。講和条約締結に関しても、もっとも先鋭的な主張を展開してい
た。新聞記者志望の学生にとっては「地方紙なら道新」みたいなあこがれの新聞社だったんです。同期入社の連中も、みんなそんなあこがれを持って全国から集まってきてい
ました。読売や毎日など全国紙に入った大学の同期もいましたが、彼らにも「いいところに入ったなあ」なんてうらやましがられました。あのころの道新はそんな新聞だった
。
それに、4歳までしか住んでいなかったにしろ、もともと北海道生まれでしょう。北海道に対してはちょっと特別な思いがありました。ただ、仙台
から札幌に行った当初は、札幌って田舎だなあと思いましたよ。仙台は人口が35万人くらいだったんじゃないかな。札幌はもっと少なかった。繁華街にしてもいかにも新開地
でね。仙台のほうがずっと洗練されていました。
とはいえ最初は札幌にはちょっとしかいなかった。釧路支社勤務だったんです。札幌から汽車に乗って釧路に向かったんですが、釧路に近づくと
窓の外にたくさん丹頂鶴がいるんですよ。びっくりしましたねえ。
今は通信手段が発達して、札幌で製作した紙面が全道に行き渡るようになっていますが、そのころはファックスすらない時代ですからね。取材執
筆から、編集作業全般、そして印刷まで、すべて北海道各地の支社が独自にやっていました。道新の場合は、釧路、旭川、函館に発行支社があった。共通するのは題字と1面の
記事くらいのもので、それぞれが札幌本社とまったく違う新聞を作っていたんです。
釧路支社は今は立派なビルになっていますが、僕が赴任したころは、赤れんがの古い建物でした。石川啄木が釧路で新聞記者をしていたことがあ
ります。釧路支社は啄木が勤務していた新聞社の社屋をそのまま使っていました。釧路港の岸壁のすぐそばだったんですが、なにせ漁師町でしょう。みんな荒っぽいんだ。殺
伐とした風情がありました。
サンマ船が夏になるとどっと入港して、釧路港に続く釧路川をサンマ船が埋めつくすんです。この季節になると、釧路の町のチンピラがみんな繁
華街から消える。チンピラよりも漁師のほうが強いんです。チンピラも漁師が怖くて逃げ出しちゃう(笑)。今でも覚えているのは、支社が港のそばだったでしょう。サンマ
船の季節に夜勤をしていたら、裏手の路地をのぞいた社員が「おお、やってるぞ」という。窓からのぞくと、酔っぱらった漁師が2人、サバ裂き包丁を持って決闘しているんだ
。1人が刺されて道に倒れた。社員たちも「やられたやられた、だれか救急車を呼んでやれや」なんていって、それで終わり。これが釧路に赴任してすぐのことだったんです。
とんでもないとこに来ちゃったなあって思いましたよ。
釧路支社では校閲部に配属されました。新人はまずは校閲か支局にまわされるのがそのころの道新の、まあ伝統というかしきたりだったんです。
校閲だと他人の原稿をチェックするだけで、自分では書けない。文章修業もして、せっかく念願の新聞社に入ったのに原稿が書けないんだから、腐っちゃってね。校閲の仲間
たちと「早く外勤記者になりたい」なんて酒を飲んでは憂さ晴らしをしていました。
そのころどんな酒の飲みかたをしていたかというと、サカナは毛ガニでした。今みたいに高級品じゃなかったんだよねえ。毛ガニがやっと商品に
なりかけていたころなんじゃないかな。冷蔵設備がなかったから、それまではなかなか出荷できなかったんでしょう。毛ガニが網にかかると、ほとんどみんな捨てていました
。もちろん地元では食べていましたよ。夜になると繁華街に毛ガニ売りが出るんです。大きな釜にお湯を煮立てて、毛ガニをどんどんゆでている。買いに行くと、ゆで上がっ
た毛ガニを新聞紙でぐるぐる包んで、荒縄で縛ってぽんと渡してくれる。この毛ガニがまたでかいんです。1つ食べると満腹です。毛ガニも今はみんな小さくなっちゃいました
ね。この毛ガニ売りから毛ガニをたくさん買ってきて、新聞用紙を巻くロール紙を破ってばっと床に広げる。ロール紙に毛ガニをどさっと盛って、ばりばり殻を割って食べる
んです。飲むのは安い焼酎ばっかりでした。いい時代といえばいい時代でした。
そんな時に乱歩さんから「もっと小説を書いてみないか」と手紙を頂いたんですよ。道新に就職して釧路に赴任しましたなんて『宝石』の編集部
に連絡していたわけじゃなかった。なにせ小説家になるつもりがなかったんですから。乱歩さんはどうして僕の居場所を知ったのかなあ。きっと調べてくれたんでしょうね。
原稿が書きたくてしかたないころだったので、乱歩さんの手紙は渡りに船でした。もう喜んで書きましたよ。最初は「賭ける」(昭和33年2月号掲
載)かな。学生時代にフェンシングをやっていたせいもあって、スポーツを題材になにか書きたかった。「賭ける」では回想形式を使っているのですが、これは映画好きが高
じた結果なんです。ジョゼフ・L・マンキウィッツという監督がいます。「三人の妻への手紙」とか「イヴの総て」とか「裸足の伯爵婦人」とか、大好きでした。この監督が
回想形式をいかにもかっこよく効果的に使っていたんです。その手法を小説に利用してみようと思った。
「賭ける」が載ったと思ったら、3カ月連続で短編を書けといってきた。これが「淋しい草原に」(昭和33年6月号)と「ラ・クカラチャ」(同年7月
号)、「黒いエース」(同年8月号)の3作だったんです。
以後、北海道に来てから書いたものは、みんな北海道が舞台です。戦後の北海道そのものがまだまだ開拓地の面影を残していた。ちょっと西部劇
みたいな世界でした。そんな北海道の自然や風土に魅力を感じて、北海道を舞台に書くようになった。またそれが東京の読者にはよかったんじゃないかな。交通も不便な時代
。観光にしても今みたいに簡単じゃなかった。新鮮だったでしょう。
釧路の町も刺激的だったしね。「暗い海深い霧」は実際に釧路周辺で起きたスパイ事件を題材にしています。北方領土への密航事件ですね。密航
した人物を取材しようと頑張ったんですが、公安がその人物にびったり張り付いていた。どうしても会えなくて、結局、取材なしで書き上げたんです。
小説を書くようになって、旅をよくするようになりました。まあ、取材ですね。校閲って内勤だから、きちんと休みが取れるんです。休みのたび
ごとに釧路を中心にあちこち歩きまわりました。アイヌ民族と初めて出会ったのもこのころですね。阿寒湖のアイヌの人たちとはかなり付き合いました。差別と抑圧によって
犯罪に走ったアイヌ人青年を主人公にした短編なども書きましたよ。

筆を折る
高城 釧路支社に3年間いて、本社の社会部に異動になりました。喜び勇んで札幌に戻りました。社会部にはこの時は1年しかいなくて、すぐに学芸
部です。僕は不満だったんですが、小説なんか書いていたんで学芸部向きだと思われたんでしょう。本社勤務になると忙しくなった。小説を書く暇がなくなってしまった。だ
から、だんだん書かなくなった。一番たくさん書いたのが昭和37年ごろかな。1970年代に入ってからはもう書いていないでしょう。小説家・高城高としてはこのころが最後で
すね。
学芸部時代に面白いことがあったんです。連続短編の1つ「淋しい草原に」が昭和35(1960)年に東映で映画化されたんです。タイトルは「消えた
密航船」(村山新治監督)です。今なら作品が映画化といえば、お金も入れば話題にもなるんだろうけれど、そのころはねえ。いくらかお金をもらった覚えがあるけど、たい
したことなかったよ。大金だったら絶対に覚えてる(笑)。そのころ僕は学芸部で映画評を担当していましてね。のちにこの村山監督を取材する機会があって「あの映画は実
は僕が原作者なんです」って言ったら驚いてました。そんな時代ですよ。僕はといえば、1人でこっそり映画館に観に行きました。だけど、内容はまったく記憶にない。たいし
たことなかったのかな。
ーーー小説を書かなくなったのはどうしてなのですか。
高城 やっぱり新聞記者をしながら小説を書くというのはやりにくかったんですよ。当時は社内の空気としても「二足の草鞋」なんて恥ずべきこと
、みたいのがありました。「内職なんかしやがって」という感じかな。釧路支社時代には「お前はどっちが本職なんだ。小説を書き続けるのなら会社を辞めろ」なんて社内で
面と向かって言われました。
札幌勤務になってからはあまり言われなくなりましたね。もちろん僕も黙っていた。みんな知ってはいたんだろうけれど、あえて触れない。見て
見ぬふり。黙認。そんな具合でした。同僚などに「いやあ実は読んでいたんだよ」なんて言われるようになったのは、小説を書かなくなってずいぶんたってからですよ。
書かなくなったのには、もう1つ、北海道で孤立していたせいもあるんじゃないかな。釧路時代も札幌に移ってからも、小説の原稿は郵便で東京に
送っていました。ファックスもメールもないんですから、郵便だけが頼りだったんです。編集者との打ち合わせも郵便でした。
原稿ひとつ送るにもこんな調子でしたからね。おまけに僕は東京にも出ていかなかったでしょう。編集者や小説家との直接の付き合いがまずなか
ったんです。江戸川さんにも実際に会ったことがなければ、大藪さんや河野さんにも会っていません。『宝石』を読みながら、こんな作家がデビューしたのか、みんなこんな
小説を書いているのか、なんて感心していたくらいのものです。読者の反応もまったく分からなかった。
東京にでもいれば、周りからの刺激もあって、よし俺も書いてみようとなったかもしれません。北海道で孤立して書いていましたから、だんだん
熱意がなくなった。自分の才能の限界も分かってきましたしね。
たまに依頼があっても「仕事が忙しいから」って断るようになった。だけど『宝石』だけはしばらくは断れなかったな。やっぱり義理がありまし
たからね。
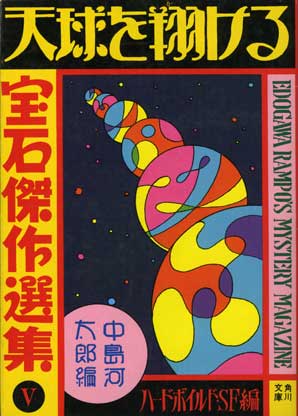
記者の歳月
高城 1970年代に入って小説を書かなくなったのには、アイヌ民族の問題に本格的に取り組み出したのも関係していますね。北海道開拓100年とかい
って、いろんな話題が取り上げられていた。だけど、なかなかアイヌ民族の問題はクローズアップされなかったんだ。僕は小説のテーマとしても取り上げたことがあったでし
ょう。新聞記者としてこのテーマを掘り下げてやろうと飛び回っていたんです。
アイヌ民族の取材を進めるうちに埴原和郎さん、藤本英夫さん、吉崎昌一さんなどなど考古学者や人類学者のみなさんとお付き合いが深まりまし
てね。埴原さんは当時、札幌医科大学にいらしたんですよ。みんなでアイヌ民族についての本を出そうということになった。これが『シンポジウム アイヌーその起原と文化
形成』です。昭和47(1972)年に北海道大学図書刊行会から出ました。あまり類書のないころだったので、かなり版を重ねたんですよ。
アイヌ民族の取材がきっかけとなって、日本人の起原に興味を持つようになりました。サハリンにも取材に行きましたし、ベーリング海峡に浮か
ぶセント・ローレンス島にもアラスカにも行きました。取材をまとめるかたちで、吉崎さんと共著で出版したのが『消えた平原べーリンジア 極北の人類史を探る』です。N
HKブックスから昭和55(1980)年に出ました。取材は楽しかったですよ。少年時代の探検家の夢がちょっと実現できた気分でした。
とにかく、新聞記者としての仕事が面白くて仕方なかったんです。大事件や大事故もあったしね。なぜか僕が夜勤の時に大きな事件が発生するん
ですよ。事件や事故に巻き込まれた人たちには申しわけないけれど、新聞記者としては記者冥利に尽きる。結婚もして子どもも生まれたし、公私ともに小説どころじゃなくな
ったというのが正直なところなんじゃないかな。
ーーー小説はもう書かないのですか。
高城 ハードボイルドはもう出る幕じゃないでしょう。1つだけ書こうと思いながら書けなかったテーマがあるんですよ。短編3部作にするつもりだ
ったんだけど、2作まで発表したところで小説を書かなくなってしまった。いつかは書こうと思っていたんだけど、今となってはね。
ーーー「高城高」は現在の乳井さんにとって、どのような存在ですか。
高城 そうですねえ、若き日の思い出ですね。青春のひとコマといったところかな。